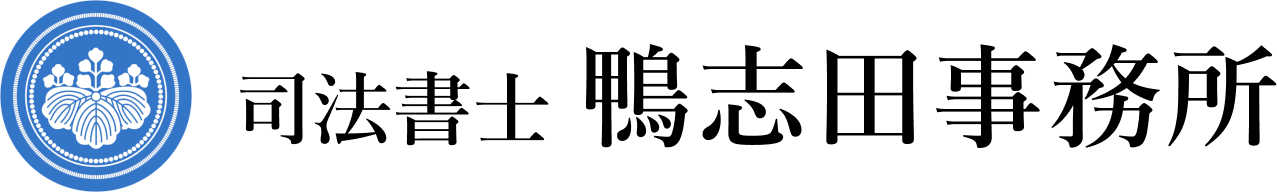Service
登記関連用語集
このページでは不動産登記を中心に登記に関係する用語を解説いたします。
【随時更新予定】
1.登記全般
①登記制度⋯誰が所有者であるかやどのような抵当権が付いているかなど、対象不動産の現在の権利関係第三者に示す制度です。そのため、所有者が住所移転を行った場合や相続の発生により名義(所有者)が変わった場合などの変更が生じた場合は速やかに登記簿の記録に反映させる必要があります。
②法務局(登記所)⋯登記手続きを行なう役所のことです。不動産の所在によって管轄(担当法務局)定められています。管轄はインターネットを利用して探すことができます。
検索方法:「〇〇市 登記管轄」
③収入印紙⋯登記手続きにおいては、登録免許税など、法務局に支払いをする時に使用する切手のようなのりの付いた小さな用紙です。法務局には印紙売り場があり、登記申請前などその場で購入できます。また、郵便局で購入することも可能です。
④登記簿謄本(全部事項証明書)⋯法務局で取得できる登記簿の記録が記載された緑色の書類です。現在事項証明書、一部事項証明書など種類がありますが、特別な場合(共有者が大変多く、全部事項証明書を取得すると膨大な枚数になってしまうなど)を除き、基本的には登記謄本(全部事項証明書)を取得すれば必要な情報が記載されていることが一般的です。
⑤補正日⋯登記申請後、補正連絡が来る可能性のある期間です。補正日を超えればそれまでに補正(訂正)の連絡がなければ、通常は無事に手続きが完了していると考えて問題ないです。なお、手続きが混雑している場合など、まれに完了していないことがありますので、その点は注意が必要です。
⑥補正⋯登記申請後、法務局から申請した登記について修正を求めることです。通常、直せる範囲のミスであれば補正の連絡にしたがって訂正すれば手続きは完了します。
⑦登録免許税⋯法務局に支払う税金のことです。収入印紙で支払うことが多いです。
⑧所有権移転登記(または持分移転登記)⋯相続や贈与、売買などにより権利が移転することで不動産の権利(持分権利も含む)を譲り受ける人に名義を変更する登記のことです。
⑨抵当権⋯金銭を借りる際に銀行などが担保として不動産(本ページでは限定して記載します)に設定する権利です。お金を期限までに返済できないと抵当権を実行して差し押さえなどを経て強制力を持つ売却手続きなどに向かっていきます。
⑩抵当権抹消登記⋯借りた金銭(住宅ローンなど)を完全に返済すると、債務が消滅します。しかし、登記簿の記録は債務が消滅しても自動でに消えることはありません。そのため、抵当権が設定されている不動産の所有者は自分でこれを抹消する登記を行なう必要があり、この登記が抵当権抹消です。根抵当権抹消登記も手続き的には同じです。
⑪住所や氏名の変更登記⋯住所や氏名の変更が生じた際に登記簿の記録を最新の状態に更新
する必要があります。この登記が住所や氏名の変更登記です。この登記は義務化が予定されておりますが、スマート登記制度という住基ネットと法務局での登記が連携する制度の開始も予定されております。詳細は法務局ホームページをご参照ください。検索時は「住所氏名変更登記義務化」や「スマート登記」で検索するとヒットしやすいです。
2.登記申請書関連
①登記の目的(登記申請書)⋯何をする登記なのかを記載します。例えば、抵当権を消す登記であれば、「抵当権抹消※◯番などここで抹消する抵当権を特定することもあります」と記載します。相続登記や贈与登記、売買登記など所有権が動く登記は「所有権移転」、「〇〇持分全部移転」などと記載します。注意が必要なのは、登記の目的には「相続登記」や「贈与登記」とは記載しないという点です。
②原因(登記申請書)⋯申請する登記の原因となった出来事の日付やその原因を記載します。例えば「〇〇年〇〇月〇〇日贈与」のようにいつ贈与したかなどを明らかにします。ただし、氏名の変更の場合は婚姻など具体的な原因ではなく、単に「氏名変更」と記載します。
③権利者(登記申請書)⋯申請する登記に関して、権利を得る者など簡単に表現すると利益を得る者のことです。例えば抵当権抹消であれば、抵当権が消えてうれしいのは抵当権を設定されていた者ですので、不動産の所有者ということになります。
④義務者(登記申請書)⋯申請する登記に関して権利を失う者など簡単に表現すると不利な状態になる者のことです。例えば抵当権抹消であれば抵当権が消えて今まで登録されていた権利が消えてしまう者となりますので、金融機関など抵当権者となります。
⑰添付情報⋯登記申請書に添付する書類や情報のことです。実際に添付する書類だけでなく、「会社法人等番号」など書類を添付せずに登記申請書に記載するに留まるものについても含んでいます。
⑤登記原因証明情報⋯登記の根拠となる事実を証明する書類のことです。例えば、抵当権抹消登記であれば、「解除証書」や「弁済証書」、相続登記については「戸籍」や「遺産分割協議書」を指します。ただし、書類のタイトルとして「登記原因証明情報」という書類もあり、この書類は名称のとおり登記原因証明情報としての役目を持ちます。
⑥登記識別情報⋯権利を取得した者が登記完了後に法務局より発行を受けた緑色の用紙に記載されたアルファベットや数字のことです。例えば、相続により所有権を引き継いだ場合や抵当権を設定した際には銀行に対して発行されます。発行時は封印されており、見られないようになっています。使用する時までは開封しないようにしましょう。いざ登記で使用する際は、シール形式のものはシールを剥がし、綴じてあるものはミシン目を切り取り開封してコピーをしてそのコピーを「登記識別情報在中」と記載した封筒に入れて法務局に提出します。
⑦登記済証⋯登記が完了した際に登記申請時に提出した書類に「受付番号や日付、法務局印」が押されたものをいいます。赤いスタンプです。相続や贈与により所有権を得た者には一般的には登記済権利証という冊子に登記済印が発行されています。手続きを当時司法書士に依頼していれば司法書士事務所の封筒に入っていることがよくあります。抵当権設定の場合には抵当権設定契約書に登記済印が押されていることが一般的です。なお、必ずこれらの書類に押されているわけではないので、ご了承ください。現在は登記済証の制度は廃止され、その代わりに登記識別情報通知が発行されるようになりました。
⑧印鑑証明書⋯市区町村で発行を受けることができる実印に関する証明書です。実印の捺印を要する登記(所有権移転の義務者、抵当権設定の義務者、相続登記の遺産分割協議に参加した相続人など)の際に法務局に提出します。原則発行から3ヶ月以内である必要がありますが、相続登記で使用する遺産分割協議書に関する印鑑証明書は発行から3ヶ月を経過しているものでも使用可能です。
⑨代理権限証明情報⋯委任状のことです。登記を誰かに代理してもらう時に委任状が必要となります。例えば抵当権抹消登記では、自分で登記する場合、銀行と抵当権の設定を受けている人がいっしょに登記をする形式(共同申請といいます)となっていますが、銀行は膨大な数ある登記を直接手続きすることはできないので抵当権抹消書類に委任状を入れて抵当権を消す人に対して委任をして任せているということが一般的です。そのため、通常は抵当権抹消登記では添付情報欄には委任状と記載することとなります。
⑩原本還付⋯登記申請時に法務局に提出した書類を返してもらうことをいいます。通常、原本還付を受けることができる書類のコピーを登記申請時に提出します(還付するためには原本還付の記載、「原本に相違ない旨」や氏名、登記申請印の捺印など形式に沿って行なう必要があります)。多くの書類が還付(返却)を受けることができますが、印鑑証明書(相続における遺産分割協議書に関係する印鑑証明書は還付可)、委任状は還付を受けることができませんので原本はそのまま法務局で保管されることとなります。
⑪会社法人等番号⋯法人(銀行や不動産会社など)には法務局から指定された番号があります。登記申請時この番号を記載することが求められる登記があります(金融機関の抵当権抹消登記や法人が当事者となる贈与登記など)。抵当権抹消登記の場合は、会社法人等番号は通常、銀行書類に別紙で案内が同封されているか、委任状の銀行名、代表者名等が記載されている箇所の近くに記載されています。不明な場合には「登記・供託オンライン申請システム」内の「商号調査」から調べることができます(システムへの登録が必要なようです。詳細は該当のホームページをご確認ください)。
3.相続登記
①相続登記⋯不動産の所有権をもち登記している人が亡くなった際に、相続人や遺贈を受けた人に名義を移す登記のことです。土地については所有権のある者については登記していることが一般的なので、登記する必要がありますが、建物(特に古い建物やごく小規模な建物)については固定資産税納税通知書に記載があっても登記されていないというケースが稀にあります。この場合は相続登記は不要です。(見分け方→固定資産税納税通知書の不動産が記載されている部分に「家屋番号」の記載がない場合には登記していない物件です)
②相続の種類
(1)法定相続⋯民法ので定められている割合で相続する方法です。遺産分割協議という話し合いは不要ですので話し合いをすることなく登記可能ですが、複数名相続人がいる場合は原則、相続人全員共有となりますので注意が必要です。特に相続登記後売却を予定している場合は相続人全員で手続きを行なう必要があります。また、手続きの方法によっては権利証(登記識別情報通知)が発行されない相続人が出てくる場合があります。
(2)相続人全員による話し合い(遺産分割協議)⋯相続人全員による話し合い(相続放棄の手続きを家庭裁判所で行った方を除く)で遺産の引き継ぎ方を決める方法です。話し合いの結果を遺産分割協議書という書類にして相続登記や必要に応じて銀行預貯金に関する相続手続きに使用します。この書類には話し合いをした相続人全員が実印で捺印し、印鑑証明書を用意する必要があります。なお、この印鑑証明書について登記においては有効期限はありません。
※遺産分割協議で財産を一切受け取らないとしても、法的な意味(裁判所で手続き
を行う)相続放棄とは法律上の意味や効果が異なります。被相続人の借金などの負債も含めて相続しないことを債権者に主張できるようにするには、裁判所で行う相続放棄の手続きが必要となりますので注意が必要です。なお、相続放棄には注意点がございますので、相続放棄の解説も併せてご参照ください。
(3)遺言書による相続⋯亡くなった方が生前に作成した遺言書に基づき、手続きを行なう相続です。
その他
・銀行ローンの借り換え⋯金利の関係などにより、ローンを組んでいる銀行を乗り換えて、条件のよい別の銀行でローンを組み直すことを一般的に指します。具体的には新しくローンを組む銀行から融資を受けて、今までの銀行で完済手続きを行います。次に(ほぼ同時に)新しくローンを組んだ銀行から抵当権の設定を受けます。これら一連の手続きに前の銀行に関しては「抵当権抹消登記」を、新しい銀行については「抵当権設定登記」を行なう必要があります。